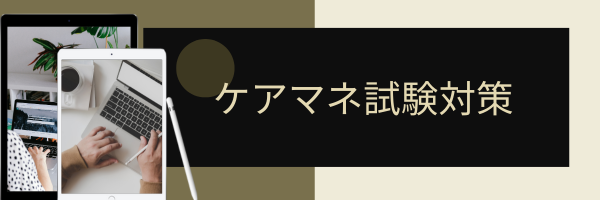前期高齢者
65〜74歳
後期高齢者
75歳以上
増加してる
後期高齢者
高齢者人口 (65歳以上)
約3600万人
前期高齢者
約1700万人
後期高齢者
約1900万人
要支援・要介護認定者数 2023年
約700万人(高齢者5人に1人)
実際にサービスを利用している人
約570万人
介護保険スタート時 認定者数
約200万人
要介護認定者数順位 (への字をイメージ)
要支援1<要支援2<要介護1>要介護2>要介護3>要介護4>要介護5
総世帯数 (令和3年)
約5100万世帯
65歳以上の者のいる世帯
約2500万世帯 (約49.7%)
65歳以上の者のいる世帯 類型
1夫婦のみの世帯
2単独世帯
3親と未婚の子のみの世帯
要介護・要支援認定者数
680万人 (令和2年)
被保険者全体の 約18.7%
認定者数 年齢別
65歳以上75歳未満 11%
75歳以上85歳未満 33%
85歳以上 54% 半数以上

要支援認定を受けている世帯 1位
単独世帯
要介護者のいる世帯 1位
核家族世帯(ほとんどが夫婦世帯)
主な介護者 内訳トップ3
1位:同居の家族
2位:事業者
3位:別居の家族(親族)
家族介護者 内訳トップ3
1位:配偶者
2位:子
3位:子の配偶者
主な介護者 男女比
男3:女7(要介護者、被虐待者同様)
主な介護者 老老介護
65歳以上…約半数
社会保障 方式 ②
1:社会扶助方式 (財源 公費と保険料)
2:社会保険方式 (財源が公費)
社会保険 ⑤
1:医療
2:年金
3:雇用
4:労災
5:介護
介護保険 保険3類型
短期保険
地域保険
強制保険
医療保険 3
自営業者保険
被用者保険
高齢者保険
医療保険 自営業者保険 2
国保
国保組合
医療保険 被用者保険 4
協会けんぽ
健康保険組合
共済組合
船員保険
医療保険 高齢者保険
後期高齢者医療制度
老人福祉法 → 介護保険法 制度
措置(行政) → 契約(本人)
老人福祉法 窓口
市町村
老人保健法 窓口
病院
介護保険加入
強制(強制適用、強制加入、強制保険)
介護保険法 第1条 介護保険制度の目的 ④
1:尊厳の保持
2:自立した日常生活
3:共同連絡の理念
4:保健医療の向上 福祉の増進
介護保険法 第2条 保険給付の理念 ⑥
1:要介護状態等の軽減・悪化の防止
2:医療との連携
3:被保険者に基づくサービス提供
4:多様な事業者等によるサービス提供
5:被保険者への必要な保険給付
6:居宅のおいて能力に応じた自立した日常生活
介護保険法 第4條 国民の努力及び義務 ③
1:健康の保持増進
2:その有する能力の維持向上
3:共同連帯の理念に基づき、費用を公平負担
2005年 改正
要介護1の一部を要支援2とする。
地域支援事業の創設
地密サービス、地域包括 創設
居住費、食費を保険給付より削除
低所得者向け補足給付の創設
情報の公表義務づけ
介護支援専門員資格更新制度
2011年 改正
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防・日常生活支援総合事業創設
居宅介護支援 権限係
市町村 (2018年4月〜)
介護予防支援 権限係
市町村
居宅サービス 権限係
都道府県
施設サービス 権限係
都道府県
地域密着型サービス 権限係
市町村
権限 ⑥
1:指定
2:指定更新
3:効力停止
4:指定取消
5:指導・監督
6:名称公示
施設サービス ③
1:介護老人保険施設
2:介護老人保健施設
3:介護医療院
居宅サービス 13
1:訪問介護
2:訪問看護
3:訪問入浴
4:訪問リハビリ
5:通所介護
6:通所リハイビリ
7:短期入所生活介護
8:短期入所療養介護
9:福祉用具貸与
10:特定福祉用具販売
11:住宅改修
12:特定施設入居者生活介護
13:居宅療養管理指導
地域密着型サービス 9
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
立入検査 市町村
全ての事業所、施設 可能
立入検査 都道府県
権限の範囲 (施設サービス、居宅サービス)
大都市特例
大都市特例 ②
指定都市(人口50万人以上)
中核市(人口20万人以上)
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員
入居定員29人以下
特定施設 種類
有料老人ホーム
軽費老人ホーム
養護老人ホーム
サ高住(サービス付高齢者向住宅)
普通徴収 納期 徴収猶予 決定
市町村条例
介護認定審査会 委員 定数 決定
市町村条例
第1号被保険者(65歳以上) 保険料率 基準額 決定
市町村条例
指定情報公表センター 指定
都道府県
普通地方公共団体
都道府県、市町村
特別地方公共団体
特別区、広域連合、一部事務組合
指定市町村事務受託法人 指定
都道府県知事
被保険者 ポイント 6
要件
適用除外
住所地特例
資格の得喪
届出
被保険者証
第1号被保険者 要件
65歳以上+住所(住民票)
第2号被保険者 要件
40歳以上65歳未満+住所(住民票)+医療保険加入
被保険者にならない
住所なし(外国に住む、在留期間3ヶ月未満の外国人)、医療保険未加入(2号)適用除外施設
国籍は日本でも海外に住んでいる
社会保険⑤
1:医療
2:年金
3:雇用
4:労災
5:介護
適用除外要件(施設)③
1:救護施設(生活保護法)
2:指定障害者支援施設(障害者総合支援法)
3:医療型障害児入所施設(児童福祉法)
資格の取得
当日
資格の喪失
翌日
例外(当日に資格を喪失)②
1:同じ日に転出と転入をした
2:第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった日
届出義務 1号 2号
1号 届出必要
2号 届出不要
第1号被保険者届出義務 ⑦
1:転入または適用除外施設退所
2:住所地特例適用時
3:氏名変更
4:同一市区町村内で住所変更
5:世帯主の変更
6:転出・死亡による資格喪失
7:外国人65歳になったとき
※年齢到達のよる届出の規定はない。年齢を迎えれば、自動的に被保険者となる。
年齢到達日
誕生日の前日 (民法)
住所地特例対象施設③
1:介護保険施設 (特養・老健・療養型・介護医療院) 2000年
2:老人ホーム(有料・軽費・養護) 2006年
3:サ高住(2015年4月〜) 2015年
住所地特例適用届 提出先
もといた市町村
転出届とセットで提出
A市→B市 住所地特例 地域支援事業
B市利用可(※2015~)
A市→B市 住所地特例 地密サービス
B市利用可(※2015~)
外国人 住所あり(住所要件満たす)
被保険者なる 在日外国人(特別永住者)
中長期在留者(3ヶ月以上在留)
被保険者証 交付
1号→交付
2号→原則交付されない
2号 交付要件 ②
1:認定申請時
2:交付申請時
保険事故とは
要介護 要支援状態
要介護状態
6か月にわたり、継続して常時介護が必要と見込まれる状態
要支援状態
6か月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に資する支援を要する。
要介護認定(要支援認定) 基準
全国一律の客観的な基準
第2号保険者 認定要件
特定疾病
特定疾病16
1:がん末期
2:関節リウマチ
3:筋萎縮性側索硬化症
4:後縦靱帯骨化症
5:骨折を伴う骨粗鬆症
6:初老期のおける認知症
7:ーキンソン病関連疾患
8:脊髄小脳変性症
9:脊柱管狭窄症
10:早老症
11:多系統委縮症
12:糖尿病性神経障害
13:脳血管疾患
14:閉塞性動脈硬化症
15:慢性閉塞性肺疾患
16:両側に膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定調査・審査、判定の基準 認定調査票
全国一律
申請時 1号被保険者 書類
申請書 介護保険被保険者証
申請時 2号被保険者 書類
申請書 医療保険被保険者証(介護保険被保険者証非交付のため)
要介護認定 住所移転後14日以内届出 有効期間
原則6ヶ月(※新規認定)
要介護認定等基準時間
実際の介護とは異なる
要介護認定 申請代行 ⑥
1:居宅介護支援事業者
2:地域包括支援センター
3:介護保険施設
4:地域密着型介護老人福祉施設
5:社会保険労務士
6:民生委員
要介護認定 代理申請 ②
1:成年後見人
2:家族
新規 認定調査 ②
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
更新 認定調査 ⑦
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:指定居宅介護支援事業者
4:地域包括支援センター
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設
7:介護支援専門員
更新認定 申請できる期間
60日前から
更新認定 できない場合(やむを得ない理由)
その理由をやんさ日から1ヶ月以内
認定 処理期間
30日以内
処理期間の延期
30日以内に、
処理見込み期間、その理由を通知
申請却下 ②
認定調査に応じない
診断命令に従わない
職権による要介護状態区分の変更
介護の必要の程度が低下のとき
被保険者 遠隔地 居住 認定調査
居住市町村に嘱託可
認定調査 基本調査項目 ⑦
1:身体機能・起居動作
2:生活機能
3:認知機能
4:精神・行動障害
5:社会生活への適応
6:特別な医療
7:日常生活自立度(認知症高齢者・障害高齢者)
主治医意見書 内容 ⑤
1:傷病に関する意見
2:特別な医療
3:心身に関する意見
4:生活機能とサービスに関する意見
5:特記すべき事項
主治医意見書 心身の状態に関する意見 認知症の中核症状 ③
1:短期記憶
2:日常の意思決定を行うための認知能力
3:自分の意思の伝達能力
主治医意見書 取り寄せるのは
市町村(保険者)※認定申請受理後
主治医がいない時②
市町村の指定する医師
市町村の職員である医師
要介護認定 判定基準
国(厚生労働省)
一次判定行為区分 ⑤
1:直接生活介護
2:間接生活介護
3:認知症の行動・真理症状(BPSD)関連行為
4:機能訓練関連行為
5:医療関連行為
2次判定必要なもの
・一次判定の結果
・特記事項
・主治医意見書
介護認定審査会 設置
市町村 (市町村の附属機関)
介護認定審査会 委員構成
保健・医療・福祉の学識経験者
介護認定審査会 委員 任期
2〜3年 市町村条例で決定
介護認定審査会 委員 任命
市町村長
介護認定審査会 開催条件
委員過半数出席
介護認定審査会 可否同数
合議体の長 決定
介護認定審査会・付帯意見 ③
1:療養に関する事項
2:留意する事項
3:認定有効期間
介護認定審査会 定数
市町村条例
介護認定審査会 会長 選出方法
委員による互選
介護認定審査会 合議体の定数
市町村条例
介護認定審査会 合議体 標準人数
5人
介護認定審査会 合議体 最低人数
3人
介護認定審査会 開催要件
委員の過半数の出席
介護認定審査会 議事
過半数を持って決し、可否同数の場合は長が決する。
認定有効期間 新規 区分変更
原則 6ヶ月
変更 3〜12ヶ月
認定有効期間 更新
原則 12ヶ月
変更 3〜36か月
※ 前回認定と同じ介護度の場合、48ヶ月まで延長可能。
広域的実施③ (介護認定審査会)
1:複数市町村による共同設置
2:都道府県への委託
3:広域連合や一部事務組合への委託
広域的実施のメリット③
1:介護認定審査会委員の確保
2:近隣市町村での公平な判定
3:認定事務の効率化
認定取消理由 市町村
要介護者に該当しなくなったとき
調査や主治医意見書の診断命令に従わない
職権による要介護認定区分の変更認定の市町村の調査の応じない。
認定事務 A市→B市 14日以内届出
調査→省略
審査・判定→省略
認定→B市認定(※認定区分そのまま) 新規認定扱(原則6ヶ月)
現物給付となる条件
居宅サービス計画の作成依頼をあらかじめ市町村に提出
自分で提出も可
保険給付の種類 ③
1:介護給付
2:予防給付
3:市町村特別給付
介護給付 対象者
要介護者
予防給付 対象者
要支援者
介護給付 サービス
居宅サービス
施設サービス
地域密着型サービス
居宅介護支援
予防給付 サービス
介護予防サービス
介護予防地域密着型サービス
介護予防支援
市町村特別給付 財源
第1号被保険者の保険料
給付方法 ②
1:現物給付方式
2:償還払い方式
介護保険サービス 償還払い
1:居宅介護福祉用具購入費支給
2:居宅介護住宅改修費支給
3:高額介護サービス費
4:高額医療合算介護サービス費
5:特例サービス費
特定入所者介護サービス費 給付方法
現物給付
特定入所者介護サービス費 対象費用
食費・居住費
特定入所者介護サービス費 対象サービス
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
高額介護サービス費 対象費用
介護保険の定率負担
高額介護サービス費(高額医療合算介護サービス費) 給付方式
償還払い(現金給付)
高額介護サービス費 対象者
すべての被保険者
高額介護サービス費 申請 ②
1:月単位
2:世帯単位
高額介護サービス費 対象外サービス ③
1:福祉用具購入費
2:住宅改修費
3:食事・居住費 その他の費用
高額医療合算介護サービス費 単位
年単位
高額医療合算介護サービス費 基準
全国一律
自己負担になる費用
食費・居住費・滞在費・娯楽費・理美容代など
1号保険料滞納ペナルティ ③
1:償還払い化
2:一時差し止.
3:減額
定率負担 減額 免除
災害 特別な事情
減額 免除 具体的内容
1:災害によって住宅等の財産が著しく損害を受けた場合
2:主たる生計者が、入院や障害、死亡、したことにより、収入の著しい減少があった場合
3:主たる生計者が事業の休廃止や失業等によって著しく減少した。
4:主たる生計者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等によって著しく減少した場合。
特例(介護予防)サービス費 支給決定
市町村
特例(介護予防)サービス費 給付方法
償還払い
特例(介護予防)サービス費 給付パターン④
1:認定申請前
2:基準該当サービス
3:離島等相当サービス
4:被保険者証忘れ
特例(介護予防)サービス費 対象外
福祉用具購入費
住宅改修費
高額介護サービス費
高額医療合算介護サービス費
介護保険に優先する給付 ③
災害補償各法律
国家公務員災害補償法
国家補償的制度
支給限度基準額④
1:区分支給限度基準額
2:福祉用具購入費支給限度基準額
3:住宅改修費支給限度基準額
4:種類支給限度基準額
区分支給限度基準額の適用外サービス ④
1:ロング
2:オリジナル
3:オンリーワン
4:ケアプラン
福祉用具購入費支給限度基準額 限度額費用
10万円
福祉用具購入費支給限度基準額 期間
1年
福祉用具購入費支給限度基準額 給付方法
償還払い
住宅改修費支給限度基準額 限度額費用
20万円
住宅改修費支給限度基準額 リセット 条件
引越し
3段階リセット
住宅改修費支給限度基準額 給付方法
償還払い
種類支給限度基準額 決定
市町村条例
支給限度基準額 上乗せとくれば ③
市町村条例
(区分支給限度基準額 福祉用具購入費支給限度基準額 住宅改修費支給限度基準額)
支給限度基準額 上乗せ 財源
第1号被保険者 保険料
保険給付 時効
2年
現物給付(法定代理受領方式) 起算日
サービス提供月の翌翌々月の1日
現金給付(償還払方式)
起算日
調整交付金 ②
普通調整交付金
特別調整交付金
普通調整交付金 内容 ②
1:第1号被保険者の所得分布状況
2:75歳以上の後期高齢者の割合
特別調整交付金 内容
災害時など特別な時
おむつ代 保険給付対象
入所系サービス(長期・短期)
長期入所サービス ⑤
1:特養
2:老健
3:介護医療院
4:地密特養
短期入所サービス ②
1:短期入所生活介護
2:短期入所療養介護
入居サービス おむつ代
原則全額自己負担
入居サービス ③
1:特定施設
2:地密特定施設
3:GH(グループホーム)
施設サービス 原則自己負担
理美容代 教養娯楽費 日常生活費
介護保険法vs原爆被爆者援護法
原爆被爆者援護法 優先
介護保険法vs戦傷病者特別援護法
戦傷病者特別援護法 優先
介護保険法vs医療保険
介護保険法 優先
介護保険法vs労災保険
労災保険 優先
介護保険法vs老人福祉法
介護保険法 優先
介護保険法vs障害者総合支援法
介護保険法 優先
介護保険&障害福祉 W指定サービス(2018年4月〜)
共生型サービス
老人福祉法 措置利用 ②
虐待高齢者、単身認知症高齢者
介護保険 会計原則
特別会計
介護保険 特別会計2勘定
保険事業勘定
介護サービス事業勘定
介護保険の事務費
市町村の一般財源
介護保険料 負担理念
共同連帯・公平負担
居宅給付費 財源構成
第1号保険料23% 第2号保険料27% 国25% 都道府県12,5% 市町村12.5%
施設等給付費 財源構成
第1号保険料23% 第2号保険料27% 国20% 都道府県17,5% 市町村12.5%
総合事業 財源構成
第1号保険料23% 第2号保険料27% 国25% 都道府県12,5% 市町村12.5%
包括的支援事業・任意事業
1号保険料23% 国38.5% 国19.25% 市町村19.25%
介護保険財政 国負担②
1:調整交付金
2:一律交付金
調整交付金②
1:普通調整交付金
2:特別調整交付金
普通調整交付金 考慮②
1号年齢階級分布(75歳以上)
1号所得分布
特別調整交付金 考慮
災害時等における保険料の減免等
第1号被保険者 保険料 徴収方法②
1特別徴収
2普通徴収
特別徴収 対象要件
年金年額18万円以上の者
特別徴収 の仕組み
年金保険者 天引 市町村へ納入
普通徴収 対象要件
年金年額18万円未満の者
普通徴収 の仕組み
市町村より納入通知書にて納入
年金 ③
老齢
遺族
障害
連帯納付義務②
1世帯主
2配偶者
財政安定化基金 設置
都道府県
財政安定化基金 財源
国1/3、都道府県1/3、市町村1/3
財政安定化基金 返還
時期計画3年(3分の1ずつ)
財政安定化基金 交付パターン
保険料未納金→2分の1
財政安定化基金 貸与
給付費増大
財政安定化基金 返済
次期3年…1/3ずつ
財政安定化基金貸付 返済金財源
第一号保険料
第2号被保険者 保険料徴収
医療保険者
第2号被保険者 保険料 被保険者→保険者
2号→医療保険者→社会保険診療報酬支払基金→市町村
1号 保険料徴収方法 ②
特別徴収(年金天引)
普通徴収(自分払い)
普通徴収・特別徴収 区別
年金年額18万円
普通徴収 納期 徴収猶予
市町村条例
生活保護受給者の保険料
福祉事務所等が、直接市町村に支払うことが可
第2号被保険者 保険料徴収
医療保険者
第2号被保険者 保険料の流れ
2号被保険者 → 医療保険者 →
→ 社会保険診療報酬支払基金 → 市町村
第1号被保険者 保険料の算定
市町村条例
第1号被保険者 保険料算定 計算方法
基準額×保険料率 (市町村条例)
保険料率 基準額 改定 頻度
3年に1度
保険料算定 所得段階
13段階 市町村条例で細分化可能
保険料滞納③
①1年以上(償還払い)
②1年半以上(一時差止)
③それでも未納(減額)
保険料 徴収猶予 規定
市町村条例
保険料 減免等
災害・天災など → 収入減少
生計維持者の死亡・障害・入院 → 収入減少
特別な理由とは、震災や水害。主たる生計維持者が
死亡したり重大な事故で入院し収入が入ってこない。
農作業の不作などがあります。
市町村条例にて、保険料減免(減額や免除)や徴収猶予する
権限 ⑥
1:指定
2:指定更新
3:指定取消
4:効力停止
5:指導監督
6:名称公示
指定基準 ④
1:法人格
2:人員
3:運営
4:設備
指定基準 決定
各権限係
指定更新 時期
6年ごと ※2006年から導入 更新制度
指定申請
事業所ごと
サービスの種類ごと
大都市特例
居宅サービス、施設サービスの権限を持てる
指定できない パターン
指定を満たしていない
申請者が刑に処させれている(禁錮、罰金)
指定取消から5年経過していない
申請前5年以内に不正・不当な行為
居宅サービス事業者 指定
都道府県
施設サービス 指定
都道府県
地域密着型サービス 指定
市町村
居宅介護支援・介護予防支援 指定
市町村
居宅サービス 13
訪問介護
訪問看護
訪問入浴
訪問リハビリ
通所介護
通所リハビリ
短期入所生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与
住宅改修
特定福祉用具販売
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
みなし指定 対象 機関
病院・診療所
薬局
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
※医療系サービス
病院・診療所 みなし指定 サービス ⑤
1:居宅療養管理指導
2:訪問看護
3:訪問リハビリテーション
4:通所リハビリテーション
5:短期入所療養介護
介護老人保健施設 介護医療院 みなし指定 サービス ②
1:通所リハビリテーション
2:短期入所療養介護
※ 訪問リハビリは別途指定を受けることで提供可
薬局 みなし指定 サービス ①
居宅療養管理指導
共生型サービス ③ 2018.4月〜
訪問介護
通所介護(地域密着型通所介護)
短期入所生活介護
共生型サービス 法律 ③
介護保険法
障害者総合支援法
児童福祉法
施設サービス ④
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
特別養護老人ホーム 根拠法
老人福祉法 許可
介護老人福祉施設 指定権限
都道府県知事
都道府県知事の許可 ②
介護老人保健施設
介護医療院
介護老人福祉施設 開設者 ③
地方公共団体
社会福祉法人
地方独立行政法人
介護老人保健施設 開設者
地方公共団体
社会福祉法人
地方独立行政法人
医療法人
国
赤十字社
健康保険組合・共済組合
介護医療院 開設者
地方公共団体
社会福祉法人
医療法人
国
赤十字社
健康保険組合・共済組合
指定の取消・効力停止
人員基準を満たさない
設備基準・運営基準を満たさない。適切な運営ができない。
不正請求があった。
命令に従わない。虚偽の報告
不正手段での指定を受けた
基準該当サービス とは?
人員基準、運営基準、設備基準を満たしていない。法人格がないなど。
特例サービス費 支給決定
市町村(保険者)
基準該当サービスとは?
人員・運営・設備基準の一部を満たしていない場合
基準該当サービス 給付方法
償還払い
基準該当サービス 基準 決定
権限 各条例
基準該当サービス 適応条件
国が定めた基準に従い、市町村が認めたとき
市町村の判断、法人格不要、非常勤で良いなど。
基準該当サービス 対象サービス ⑦
1:訪問介護
2:通所介護
3:居宅介護支援
4:介護予防支援
5:(介護予防)訪問入浴介護
6:(介護予防)短期入所生活介護
7:(介護予防)福祉用具貸与
基準該当サービス 適用外
医療系サービス
地域密着型サービス
施設サービス
基準該当サービス ③
1:基準該当居宅サービス(基準該当介護予防サービス)
2:基準該当居宅介護支援
3:基準該当介護予防支援
基準該当サービス 保険給付
特例サービス費
基準該当居宅サービス 給付費
特例居宅介護サービス費
基準該当介護予防サービス 給付費
特例介護予防サービス費
基準該当居宅介護支援 給付費
特例居宅介護サービス計画費
基準該当介護予防支援 給付費
特定介護予防サービス計画費
特例(介護予防)サービス費 ④
1:認定申請前に緊急的にサービスを利用
2:基準該当サービス
3:離島
4:被保険者証未定時
特例(介護予防)サービス費 適用外
住宅改修費
福祉用具購入費
特例(介護予防)サービス費 給付方法
償還払い
離島等における相当サービス
居宅サービス
地域密着型サービス
居宅介護支援
介護予防支援
介護予防サービス
地域密着型介護予防サービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム(介護付きのみ)
軽費老人ホーム(ケアハウス)
養護老人ホーム
サービス付高齢者向け住宅
老人福祉施設(老人福祉法)
老人デイサービスセンター
老人短期入所施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
老人福祉センター
老人介護支援センター
地域包括支援センター 設置者
2割 市町村
8割 外部委託 (社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人など)
立入調査 市町村
全事業所可能
※都道府県は、施設サービス、居宅サービスのみ
栄養ケアマネジメント加算
→基本サービスに包括
→栄養マネジメント強化加算(親切)
栄養ケア・マネジメントの未実施減算
地域支援事業 3本柱
1:介護予防・日常生活支援総合事業
2:包括的支援事業
3:任意事業
介護予防・日常生活支援総合事業 ②
1:一般介護予防事業
2:介護予防・生活支援サービス事業
包括的支援事業 ⑦
1:総合相談支援事業
2:権利養護事業
3:包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
4:在宅医療・介護連携推進事業
5:認知症総合支援事業
6:地域ケア会議推進事業
7:生活支援体制整備事業
一般介護予防事業 ⑤
介護予防把握事業
介護予防普及啓発
地域介護予防活動支援事業
地域リハビリテーション活動支援事業
一般介護予防評価事業
介護予防・生活支援サービス事業 ④
1:第1号訪問事業
2:第1号通所事業
3:第1号生活支援事業
4:第1号介護予防支援事業
一般介護予防事業 対象者
65歳以上の人すべて
介護予防・生活支援サービス事業 対象者
基本チェックリスト該当者
要支援者
継続利用要介護者
任意事業 ②
1:介護給付等費用適正化事業
2:家族介護支援事業者
介護給付等費用適正化事業 ③
1:認定調査状況チェック
2:ケアプラン点検
3:住宅改修の点検など
地域ケア会議の機能 ⑤
1:個別課題解決
2:地域課題発見
3:地域つくり・資源開発
4:政策形成
5:ネットワーク構築
包括的支援事業 2006年スタート ③
1:総合相談支援事業
2:権利養護事業
3:包括的継続的ケアマネジメント支援事業
包括的支援事業 2014年 スタート ④
1:在宅医療・介護連携推進事業
2:認知症総合支援事業
3:地域ケア会議推進事業
4:生活支援体制整備事業
第1号介護予防支援事業 委託先
地域包括支援センター
基本チェックリスト 大項目
社会参加
運動機能
栄養
口腔
閉じこもり
物忘れ
第1号介護予防支援事業 ③
ケアマネジメントA 介護予防支援同様
ケアマネジメントB サービス担当者会議 モニタリング省略
ケアマネジメントC 基本的にサービス利用開始時にみ
審査請求 内容 ④
1:認定
2:被保険者証
3:保険給付
4:保険料・徴収金
介護保険審査会 設置
都道府県
介護保険審査会 業務
市町村の行った処分に対する不服申し立ての審理・裁決(中立性・公平性)
都道府県知事の指揮監督を受けない。
介護保険審査会 委員構成
被保険者代表委員 3人
市町村代表委員 3人
公益代表委員 3人以上
※ 非常勤の特別職
介護保険審査会 委員 任期
3年
介護保険審査会 任命
都道府県知事 ※ 再認可能
専門調査員 任命
都道府県知事
合議体を構成する委員の指名
介護保険審査会
介護保険審査会 会長選出
公益代表
専門調査員 職種
保健・医療・福祉の学識経験者
(非常勤の特別職)
指定情報公表センター 指定
都道府県
介護保険事業計画 ③
1:基本指針
2:都道府県介護保険事業支援計画
3:市町村介護保険事業計画
基本指針 ③
1:サービス提供体制の確保・地域支援事業実施に関する基本的事項
2:事業計画・支援計画の作成に関する事項
3:保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
基本指針 策定・変更ルール
あらかじめ
総務大臣・その他関係機関の長に協議し
策定後公表
「医療介護総合確保法」に規定する
総合確保方針に即して定める。
都道府県介護保険事業支援計画 策定期間
3年1期
都道府県介護保険事業支援計画 定めるべき事項 ③
1:介護保険施設
介護専用型特定施設
地域密着型特定施設
地域密着型介護老人福祉施設
⇨必要利用定員総数
2:サービスの見込量
3:市町村施策&目標(自立支援・悪化防止・費用適正化)
の支援&目標
都道府県介護保険事業支援計画 定めるよう努める事項 ⑥
1:介護支援専門員(その他従業者)の確保、資質向上
2:介護サービス情報公表
3:施設生活環境改善
4:施設関連携
5:サービス円滑提供
6:市町村間連絡調整
都道府県介護保険事業支援計画 一体
都道府県老人福祉計画
都道府県介護保険事業支援計画 調和
都道府県地域福祉支援計画
都道府県高齢者居住安定確保計画
都道府県介護保険事業支援計画 整合性
都道府県計画
医療計画
都道府県介護保険事業支援計画 策定変更時 ルール
特になし
都道府県介護保険事業支援計画 策定・変更後
厚生労働大臣に提出
市町村介護保険事業計画 策定期間
3年1期
市町村介護保険事業計画 定めるべき事項 ④
1:認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
⇨ 必要利用定員総数
2:サービスの種類ごとの見込み量
3:地域支援事業の見込み量
4:施策・目標(2018年からの改正)
・自立支援
・悪化防止
・費用適正化
市町村介護保険事業計画 定めるよう努める事項 ⑤
1:見込量確保
2:各種費用の額
3:サービス円滑提供
4:地域支援事業円滑実施
5:医療、居住施策連携
見込量(人数)🟰義務事項
費用の額(額)🟰努力事項
市町村介護保険事業計画 一体
市町村老人福祉計画
市町村介護保険事業計画 調和
市町村地域福祉計画
市町村高齢者居住安定確保計画
市町村介護保険事業計画 整合性
市町村計画
市町村介護保険事業計画 策定・変更時のルール
被保険者の意見を反映させる必要な措置
都道府県の意見聴取
市町村介護保険事業計画 策定・変更後
都道府県へ提出
国保連 業務 ④
1:介護報酬審査・支払(介護給付費等審査委員会)
2:苦情受付・調査・助言
3:第三者行為求償事務
4:介護保険事業運営
苦情受付・調査・助言 機関
国保連
国保連 事業所勧告(効力停止・指定取消)
不可
介護支援専門員の義務 ⑦
1:公正・誠実な業務遂行義務
2:基準遵守義務
3:資質向上努力義務
4:介護支援専門員証の不正使用の禁止
5:名義貸しの禁止
6:信用失墜行為の禁止
7:秘密保持義務
ケアマネジメント ③
居宅介護支援
介護予防支援
施設介護支援
ケアマネジメントの流れ ⑦
1:インテーク
2:アセスメント
3:ケアプラン(原案作成)
4:サービス担当者会議
5:実施
6:モニタリング
7:終結
課題分析標準項目(基本情報に関する項目) ⑨
1:基本情報
2:これまでの生活状況と現在の状況
3:利用者の社会保障制度の利用情報
4:現在利用している支援や社会資源の状況
5:障害老人の日常生活自立度
6:認知症である老人の日常生活自立度
7:主訴・意向
8:認定情報
9:今回のアセスメントの理由
課題分析(アセスメント)に関する項目 14
1:健康状態
2:ADL
3:IADL
4:認知機能や判断能力
5:コミュニケーションにおける理解と表出の状況
6:生活リズム
7:排泄の状況
8:清潔の保持に関する状況
9:口腔内の状況
10:食事摂取の状況
11:社会との関わり
12:家族等の状況
13:居住環境
14:その他留意すべき事項・状況
介護予防支援 アセスメント4領域
1:運動及び移動
2:家庭生活を含む日常生活
3:社会参加ならびに対人関係コミュニケーション
4:健康管理
インテーク
場所、回数の規定なし
アセスメント 留意点 ② 居宅・予防
1:居宅訪問
2:利用者及び家族に面談
アセスメント 施設介護支援
入所者及び家族
ケアプラン 医療系サービス 位置付け
主治医の意見
居宅サービス計画 主治医に交付
医療系サービス
訪問看護
訪問リハビリ
通所リハビリ
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
訪問介護(生活援助)位置付け
一定回数以上の生活援助
理由の記載 市町村提出
短期入所サービス位置付け
認定有効期間の概ね半数を超えない
福祉用具の位置付け(貸与・販売)
必要な理由 記載
サービス担当者会議 継続の必要性
サービス計画に記載
介護認定審査会の意見反映
利用者の説明、理解
内容に沿って居宅サービスを作成
サービス担当者会議 開催時期 ④
1:新規
2:変更
3:区分変更
4:更新
サービス担当者会議 出席者
利用者、家族、サービス担当者、主治医など
利用者のケアに関わる人
記録の保存
完結の日から2年
サービス計画の原案
文書で説明、利用者の同意
サービス計画の交付
利用者
サービス担当者
(医療系サービス利用時は主治医)
施設介護支援について
習慣サービス計画or日課計画票 どちらか使用で良い
個別サービス計画
居宅サービス事業者 → 介護支援専門
個別サービス計画 提出義務なし ③
1:訪問入浴
2:居宅療養管理指導
3:住宅改修
居宅介護支援 モニタリング ポイント
1回以上/1月、居宅訪問
1回/1月 記録
結果の記録 完結に日から2年間保存
介護予防支援 モニタリング
1回以上/3月、居宅訪問
1回/1月 記録
居宅介護支援 効力停止/指定取消 ③
1:立入検査→是正命令無視
2:介護保険法(その他関連法)→違反
3:更新認定調査→虚偽報告
ケアプラン 2種類
1:ケアマネケアプラン
2:セルフケアプラン
セルフケアプラン→介護保険サービス利用
現物給付可(※プラン→市町村:事前届出要)
ノープラン(ケアプラン無) 保険給付費 受給方式
償還払方式(現金給付)
個別サービス計画→ケアマネ 提出義務
原則:有り
例外:無し(訪問入浴介護計画、居宅療養管理指導計画)
指定介護予防支援 担当職員⑤
1:保健師
2:社会福祉士
3:介護支援専門員
4:経験のある看護師
5:高齢者保健福祉に関する相談業務に3年以上従事した社会福祉主事
介護支援 課題分析 アセスメント 4領域
1:運動・移動
2:家庭生活を含む日常生活
3:社会参加、対人関係、コミュニケーション
4:健康管理
定めるべき事項
見込み量 🟰 人
定めるよう努める事項
費用 🟰 お金
訪問看護 提供事業所(指定) ②
1:病院・診療所(みなし指定)
2:訪問看護ステーション
訪問看護 専門職
看護師
准看護師
保健師
理学療養士
作業療法士
言語聴覚士
訪問看護 内容 ⑧
1 :病 状 察 、 情 報 収 集 、
2 :療 養 上 の 世 話 、
3 診療の補助、
4:精神的支援、
5:リハビリテーション、
6:家族支援、
7療養指導、
8:看取り支援(在宅)
24時間体制 加算
緊急時訪問看護加算
複数名加算 算定要件
一人での訪問が困難
暴力行為、迷惑行為、器物破損など
上記の内容に準ずると認められる時
退院時共同指導加算 算定
退院または退所1回につき1回
(特別な管理が必要な場合は2回可)
ターミナルケア加算 算定
死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施
24時間連絡体制
特別管理加算 算定
真皮を越える褥療
カニューレ、カテーテル、
透析、点滴、在宅酸素療法など。
GH 訪問看護利用
医療保険のみ可
訪問看護ステーション 利用流れ
医師指示書⇨計画書⇨報告書
病院・診療所 利用流れ
診療記録可
訪問看護ステーション 管理者
保健師または看護師
訪問看護ステーション 人員基準
看護職員(保健師・看護師・准看護師)
常勤換算2.5人以上(うち一人は常勤)
機能訓練士 ⇨ 適当数
病院・診療所(みなし指定)人員基準
適当数
同居家族への提供
提供の禁止
看護師等
看護師
保健師
訪問看護指示書 作成
保健師
看護師
医療保険と介護保険 優先
介護保険
医療保険から提供 ③
1: 特別訪問看護指示書
2:精神科訪問看護示書(認知症診断 ×)
3:指定疾患
特別訪問看護師指示書 ③
急性増悪時
退院時
終末期
指定疾患 例
末期がん、多発性硬化症、ハ ンチントン病、筋参縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関 連疾患、プリオン病 など
特別訪問看護師指示書 保険
医療保険
特別訪問看護師指示書 期間
14日(毎日提供可)
※気管カニューレ使用・真皮を超える褥瘡、これに該当する患者は28日間医療保険対象
訪問看護指示書 有効期間
6ヶ月
医療系サービス ⑦
訪問看護
訪問リハ
通所リハ
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
訪問看護 同時算定不可
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
定期巡回随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型 特定施設入居者生活介護
看護小規模多機能型居介護
みなし指定 ③ (提供機関)
1:病院・診療所
2:介護老人保健施設
3:介護医療院
リハビリテーションの分類 ③
急性期
回復期
生活期(維持期)
医療保険 対応 リハ ②
1:急性期リハ
2:回復期リハ
訪問リハビリテーション費 算定
週6回限度
※ 退院・退所日から3ヶ月以内は、週に12回を限度(2021年〜)
人員基準 医師
常勤 1人以上
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 人員基準
1人以上 (常勤・非常勤等の定めなし)
要支援1・2 リハ 内容
予防的リハ
要介護1・2 リハ 内容
自立支援型リハ
要介護3・4・5 リハ 内容
介護負担軽減型リハ
みなし指定 ③
1:病院・診療所
2:介護老人保健施設
3:介護医療院
通所リハビリテーション費 算定 ③
1:事業所規模 (通常規模、大規模)
2:時間
3:介護度
人員基準 医師
常勤 1人以上
人員基準 医師
医師、理学療法士、作業療法士
(専らサービス提供にあたる看護師に代行可能。)
人員基準 PT.OT.ST 看護職員 介護職員
利用者 10:1
人員基準 PT.OT.ST
100:1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 スタート
2012年 (地域密着型サービス)
対象者
要介護者
類型 ②
一体型 (訪問看護が含まれている)
連携型
報酬
月単位の定額制(区分支給限度基準額の対象)通所系サービス減算あり
提供サービス ④
定期巡回サービス
随時対応サービス
随時訪問サービス
訪問看護サービス
計画作成責任者
社会福祉士
介護支援専門員
介護福祉士
医師
保健師
看護師(准看護師含む)
オペレーター
社会福祉士
介護支援専門員
介護福祉士
医師
保健師
看護師(准看護師)
1年以上経験のあるサービス提供責任者
介護・医療連携推進会議 頻度
6ヶ月に1回
2018年度から6ヶ月に1回になった、以前は3ヶ月に1回
サービススタート
2012年(以前は複合型サーボス、2015年〜看多能)
対象者
要介護者
対象サービス ④
訪問
通い
泊り
訪問看護
人員基準 管理者
3年以上認知症介護経験➕認知症サービス事業者管理者研修を終了
保健師もしくは看護師
人員基準 看護職員
従業者1人以上、常勤の保健師または看護師
常勤換算2.5人以上
人員基準 日中(通い)
常勤換算3:1 (1人以上は看護職員)
人員基準 介護支援専門員
1人以上 兼務可 研修修了者
★人員基準
| 日中(通い) | 常勤換算3:1 ※1人以上は看護職員 |
| 日中(訪問) | 常勤換算2人以上 ※1人以上は看護職員 |
| 夜間(夜勤) | 時間帯を通して1人以上 ※宿泊者なし、おかなくていい。 |
| 夜間(宿直) | 時間帯を通して1人以上 |
| 看護職員 | 常勤換算2.5人以上 ※1人以上は常勤の保健師または看護師 |
| 介護支援専門員 | 1人以上・兼務可 研修修了者 |
登録定員および利用定員
| 本体事業所 | サテライト事業所 | |||
| 登録定員 | 29人まで | 18人まで | ||
| 通いサービス | 18人まで | 登録定員の 1/2から12人まで | ||
| 宿泊サービス | 通いサービス定員の 1/3から9人 | 通いサービス定員の 1/3から6人 |
計画書の作成
居宅サービス計画 → ケアマネ
個別計画 → ケアマネ
看護小規模多機能型居宅介護報告書(訪問看護利用) → 保健師か看護師
運営推進会議 頻度
2ヶ月に1回
併用可能サービス
訪問リハビリ
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修
居宅療養管理指導
フレイル ⑤
体重減少
握力低下
疲れやすさ
歩行速度低下
身体活動レベル低下
※3項目以上であればフレイル
サルコペニア
加齢性筋肉減少症
筋肉低下、筋萎縮
指輪っかテスト 検査法
関節リウマチ
自己免疫疾患(サイトカインが関節の表面の滑膜の炎症起こす)
多発性で左右対称
手指、手関節、肘など (第二関節が腫れる)
(症状)
朝のこわなばり ⇨ 1時間以上続く
関節の変形・不安定・熱感 ⇨
頸椎破壊 ⇨ 痺れなどの神経症状
脊柱管狭窄症
(原因)
脊柱管が狭くなり、脊髄が圧迫される。
(症状)
腰痛、下肢痛、痺れ
間欠性破行(歩くと痛む、立ち止まると痛みが軽減)
高齢者に多い骨折
・大腿骨頸部骨折
転倒が原因 ADLが大きく低下
手術→早期離床→リハビリ→
(予防)
骨粗鬆症の予防、転倒リスク軽減、環境設定(ヒッププロテクター)
・胸腰椎圧迫骨折
・橈骨遠位端骨折
・肋骨骨折
| 名前 | 特徴 |
| アルツハイマー型 | βタンパク質に異常蓄積(老人班) エピソード記憶 近時記憶の障害が著しい |
| 脳血管性 | 脳梗塞や脳出血が原因 不可逆的 段階的に進行 |
| レビー小体型 | リアルな幻視 パーキンソン症状 自立神経障害 転倒 便秘 |
| 前頭側頭型 | 前頭葉、側頭葉に萎縮が見られる |
老健 開設者
地方公共団体
医療法人
社会福祉法人
国民健康保険団体連合会
日本赤十字社
医療保険者
老健 人員基準 規定人員8
1:医師
2:薬剤師
3:介護職員、看護職員
4:支援相談員
5:PT、OT、ST
6:栄養士または管理栄養士
7:介護支援専門員
8:調理員、事務員、その他
施設 感染症対策委員会 開催
1回/3ヶ月
バイスティクの7原則
1個別化の原則 2意図的な感情表出の原則 3統制された情緒的関与の原則 4受容の原則
5非審判的態度の原則 6自己決定の原則 7秘密保持の原則
α:専門的援助関係の原則
訪問介護 内容③
1身体介護 2生活援助 3通院等乗降介助
生活援助 NGパターン③
1利用者以外に対する行為
2非日常的な行為
3過度な行為
定員
19人以上
通所介護 人員基準 ⑤
管理者 生活相談員 看護職員 介護職員 機能訓練指導員
管理者 資格
不要 常勤 専従
生活相談員
専従 1人以上
※確保すべき勤務延時間数には、サービス担当者会議、地域ケア会議などの時間も含まれます。
看護職員
看護師 准看護師 単位ごとに専従 1人以上
介護職員 資格
不要
※認知症介護基礎研修受講 2024年3月末までは努力義務
機能訓練指導員 資格要件 ⑦
1:PT (理学療法士)
2:OT (作業療法士)
3:ST (言語聴覚士)
4:看護職員
5:柔道整復師
6:あんまマッサージ指圧師
7:はり師・きゅう師
介護報酬 算定基準 ③
1:事業所規模 3
2:利用時間 6
3:要介護状態区分 5
お泊まりデイ
都道府県に届出 2015年〜
通所介護計画 作成
管理者作成
個別機能訓練加算
機能訓練指導員等 訪問 計画作成 3月1回 訪問
目的③
1:社会的孤立感の解消
2:心身機能の維持
3:利用者家族の負担軽減
類型③
1:単独型
2:併設型
3:空床利用型
単独型 定員
定員20人以上
併設型 定員
定員20未満も可 定めなし
空床利用型
定員20未満も可 定めなし。 空いたベッドを利用
居室定員
4人以下
短期入所生活介護計画 作成担当 期間
作成:管理者 期間:4日以上利用
※ケアマネ在籍時取りまとめケアマネ望ましい
認知症系の加算
ダブル算定不可
おむつ代
保険給付対象
住宅改修 ⑥
1:手すりの取り付け
2:段差の解消
3:床または道路めんの材料の変更
4:引き戸等への扉の取り替え
5:洋式便器への変更
6:付帯工事
住宅改修費支給限度基準額
20万円 ※一住宅 同一住居複数要介護者→それぞれ支給可
住宅改修費 再給付 ②
1:3段段階リセット
2:引越し
特定福祉用具販売 ⑥
1:腰掛け便座
2:自動排泄処理装置(交換可能部分)
3:排泄予想支援機器
4:入浴補助用具
5:簡易浴槽
6:移動用リフト(釣り具)