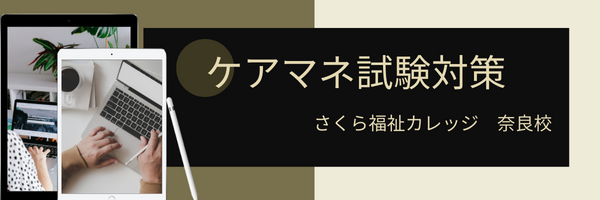問題1 高齢化について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 2025(令和7)年には、いわゆる団塊の世代が85歳に到達する。
2 2021(令和3)年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯「三世代世帯」の割合が一番多い。
3 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計 (全国推計)」(平成30年推計)によると、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増加し続ける。
4 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(平成29年推計) によると前期高齢者の人口は、2015 (平成27) 年と比べて2045 (令和27) 年では倍増する。
5 2019(令和元)年度末における85歳以上の介護保険の被保険者に占める要介護又は要支援と認定された者の割合は、50%を超えている。
解答 3・5
1 2025年問題についてですね。団塊の世代(1947年〜1949年生まれ)の人が75歳。後期高齢者になり、社会保障費の増加や働き手が不足するという問題です。
2 65歳以上の者がいる世帯は、約2580万世帯です。
①夫婦のみの世帯 ②単独世帯 ③親と未婚の子のみの世帯 ④三世代世帯の順番です。
単独世帯は増加 三世代世帯は減少しています。
3 設問の通りです。特に単独世帯、夫婦のみの世帯が増加しています。
4 2018年を境に、後期高齢者が前期高齢者を上回っています。今後は後期高齢者の人口は増加されると予想されます。
5 設問の通りです。85歳上の被保険者の占める、要介護又は要支援者の認定を割合は、50%を超えています。
総世帯数 (令和3年)
約5100万世帯
65歳以上の者のいる世帯
約2500万世帯 (約49.7%)
65歳以上の者のいる世帯 類型
1夫婦のみの世帯
2単独世帯
3親と未婚の子のみの世帯
要介護・要支援認定者数
680万人 (令和2年)
被保険者全体の 約18.7%
認定者数 年齢別
65歳以上75歳未満 11%
75歳以上85歳未満 33%
85歳以上 54% 半数以上
問題2 地域福祉や地域共生社会について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 市町村は、包括的な支援体制を整備するため重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。
2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする。
3 地域共生社会とは、子供・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創 り、高め合うことができる社会のことである。
4 介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が解決が困難な地域生活課題を把握したときは、その事業者が自ら課題を解決しなければならない。
5 高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスは、介護保険制度と障害福祉制度の両方に位置付けられている。
解答 2・3・5
1 重曹的支援体制整備事業は、実施を希望する市町村による任意事業です。「実施しなければならない」は間違いとなります。
2 市町村地域福祉計画は、市町村が策定するのですが、市町村の努力義務となります。
3 設問の通りです。
4 事業者が課題解決に努力することは必要ですが、全て事業者で解決が難しい場合もあります。行政、各事業所、インフォーマルサポートなどが協力して、解決に向かうことが理想です。
5 設問の通りで、共生型サービスの内容となります。共生型サービスは、2017年の改正で創設されました。
問題3 社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 雇用保険は、含まれない。
2 自営業者は、介護保険の被保険者にならない。
3 医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。
4 年金保険は、基本的に任意加入である。
5 財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。
解答 3・5
1 社会保険ときたら、医療、年金、雇用、労災、介護と覚えておきましょう。雇用保険は社会保険に含まれます。
2 介護保険も社会保険の一つなので、要件を満たすと強制的に被保険者となります。年れによって、1号、2号と分かれます。自営業者や被用者のよって被保険者の有無が変わるわけではありません。
3 設問の通りです。医療保険は業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とします。
4 年金保険だけでなく、社会保険は要件を満たせば、強制的に加入する必要があります。
5 社会保険の特徴として、財源に保険料が加入する人の保険料が入っていることが特徴です。介護保険もそうですが、租税(税金)も税源に含まれています。
問題 4 介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選 べ。
1 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければならない。
2 被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。
3 可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されな ければならない。
4 医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
5 介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供が行われなければならない。
解答 1・3・4
介護保険法第2条は、キーワードを暗記してきましょう。
内容としては保険給付のことです。
・要介護状態等の軽減又は悪化の帽子
・医療の連携
・
問題 5 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3 つ選べ。
1 介護老人福祉施設
2 地域密着型介護老人福祉施設
3 有料老人ホーム
4 介護老人保健施設
5 認知症対応型共同生活介護
解答 1・3・4
まずこの問題を解くにあたり基礎的な話をしておきたいと思います。
介護保険は、「住所地主義」と言って、住所地(住民票)のある市町村の被保険者になります。
引っ越しなどをして住所が変わった場合は、保険者も変わります。
住所地特例対象施設に入所や入居した場合はどうなるでしょうか。
施設に入所するわけですから、住所は変わりますが、保険者はもともと市町村のままです。これが住所地特例の試験ポイントになります。
住所地特例対象施設③
介護保険施設 (特養、老健、療養型、介護医療院)
老人ホーム (有料、軽費、養護)
サ高住
上記の内容は暗記しておくこと大切です。
この問題は、介護老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、この3つが「住所地特例」と選ぶことができますね。
問題6 65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものはどれか。2 つ選べ。
1 老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者
2 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者
3 生活保護法に規定する更生施設の入所者
4 生活保護法に規定する救護施設の入所者
5 児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者
解答 2・4
適用除外施設についての問題ですね。
設問では「65歳以上の者であって・・・」とありますので、第1号被保険者について考えていくといいですね。
第1号被保険者の要件はOKでしょうか?
「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」 です。
この要件を満たすと、自動的に被保険者となります。介護保険は社会保険の一つで、強制加入となります。特徴として、強制保険、地域保険、短期保険などがあります。
被保険者要件を満たしていても、被保険者にならない例外があり、これが適用除外施設に入所・入院している場合です。
どうしてか? 簡単に言うと、介護保険を利用しないからです。つまり、介護保険を利用しないので、保険にも加入しない事になります。その人の支援や介護は、介護保険法でななく、他の法律を根拠にした給付を受ける事なります。
適用除外施設はたくさんありますが、試験対策として3つ覚えましょう。
1 救護施設(生活保護法)
2 障害者支援施設(障害者支援施設)
3 医療型障害児入所施設(児童福祉法)
問題 7 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
2 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおい て、介護保険に優先する。
3 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
4 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
5 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
解答 1・2・3
介護保険による給付と、他の法律による給付が重複する場合。どちらが優先するのかが問われています。
簡単にまとめると。
介護保険法 < 災害補償各法 国家補償的制度
介護保険法 > 老人福祉法
※ 老人福祉法による措置。介護放棄や虐待など。
介護保険法 > 医療保険各法
介護保険法 > 生活保護法
介護保険法 > 障害者総合支援法
例えば、訪問看護サービスは、医療保険からも介護保険からも提供されます。
原則は介護保険からが優先的に提供さます。
試験対策としては、問題文をよく読んで、どちらが優先か間違わないようにすることです。
問題 8 介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。 2 つ選べ。
1 居宅介護サービス計画費の支給
2 特定入所者介護サービス費の支給
3 居宅介護福祉用具購入費の支給
4 高額介護サービス費の支給
5 高額医療合算介護サービス費の支給
解答 1・3
介護保険の保険給付の方法は、現物給付と償還払い、二つ種類があります。現物給付化されているものがほとんどです。現物給付を簡単にまとめると、利用者さんはサービスを受けて、原則1割の利用料を支払います。残りの9割は事業所が市町村(国保連に委託)に請求します。
試験ポイントとしては、償還払いになる保険給付を覚えておきましょう。
居宅介護福祉用具購入費
居宅介護住宅改修費
高額介護(予防)サービス費
高額医療合算介護(予防)サービス費
特例サービス(介護予防)費
問題 9 介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として正しいものはどれか。 3 つ選べ
1 医師の診断書に基づき居宅サービス計画を作成しなければならない。
2 要介護者のため忠実に職務を遂行しなければならない。
3 自らサービスの質の評価を行うこと等により常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない。
4 利用者が居宅において心身ともに健やかに養護されるよう、利用者の保護者を支援しなければならない。
5 法令遵守に係る義務の履行が確保されるよう業務管理体制を整備しなければならない。
指定介護保険事業者とくれば、13あります。
1:訪問介護
2:訪問看護
3:訪問入浴
4:訪問リハビリ
5:通所介護
6:通所リハビリ
7:短期入所生活介護
8:短期入所療養介護
9:福祉用具貸与
10:特定福祉用具販売
11:住宅改修
12居宅療養管理指導
13:特定施設入居者生活介護
1 そのような決まりはありません。居宅サービス計画は、利用者さんからアセスメントしたり、ご家族の意見、主治医の意見者や認定調査の結果を参考にしながら作成されます。
2 その通りです。
3 その通りです。もっともらしい内容ですね。
4 健やかに養護されるよう」「保護者を支援」という表現が少し違和感を感じるところです。
これは児童福祉法において規定されています。介護保険法ではありません。
5 介護保険法第115条において、「介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられている」と規定されています。内容的に気になる部分はないかと思います。
問題10 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計 画を作成するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。
3 都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。
4 厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及 び分析を行い、その結果を公表するものとする。
5 厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供 するよう求めることができる。
解答 1・4・5
2 分析するように努める必要があります。
3 都道府県ではなく、厚生労働大臣
問題 13 地域支援事業の包括的支援事業として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 家族介護支援事業
2 一般介護予防事業
3 在宅医療・介護連携推進事業
4 保健福祉事業
5 生活支援体制整備事業
解答 3・5
過去問にも同じような問題が出題されたことがあると思います。地域支援事業は事業名の暗記が必須です。すぐには覚えられませんので、何度も反復することが大切。
地域支援事業は3本柱からなります。
1介護予防・日常生活支援総合事業 2包括的支援事業 3任意事業
包括的支援事業は7つあります。
1 総合相談支援事業
2 権利擁護事業
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
4 在宅医療・介護連携推進事業
5 認知症総合支援事業
6 地域ケア会議推進事業
7 生活支援体制整備事業
任意事業は2つです。
1 家族介護支援事業者
2 介護給付等費用適正化事業
問題16 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護支援専門員の資格に関する処分
2 指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分
3 財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分
4 要介護認定に関する処分
5 被保険者証の交付の請求に関する処分
解答 4・5
介護保険の保険者である市町村は、被保険者に対して処分、決め事をします。要介護、要支援認定もそれにあたります。その内容に不服がある時は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に審査請求(不服申し立て)行うことができます。
ポイントとしては、保険者、被保険者、この2者間が関わる内容であることです。
設問では、審査請求できる内容が問われています。
暗記しておきましょう。
・要介護(要支援)に関する処分
・被保険者証の交付の関する処分
・保険給付に関する処分
・保険料、徴収金に関する処分
1 介護支援専門員に資格に関する処分は、介護保険審査会への審査請求の内容ではありません。
2 指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分は、介護保険審査会への審査請求の内容ではありません。審査請求の内容は、保険者が被保険者に対しての内容です。
3 財政安定化基金拠出金に関する処分は、審査請求の対象になりません。
4・5 審査請求が認められる内容です。
問題17 介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10 年である。
2 法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2 年である。
3 滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
4 介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
5 介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
解答 2・4・5
1 償還払いとは、一旦全額を支払い、保険給付が対象になる分を保険者に請求することです。介護保険に加入している被保険者は、必要な保険給付を受けると権利がありますが、時効が決まっています。2年です。10年は長すぎますね。
2 設問の通り、法定代理受領方式の場合でも2年になります。
3 滞納した介護保険料の徴収権は2年で消滅します。この場合が、保険給付は9割から7割に減額されます。保険料を滞納した場合は、ペナルティーが課せられます。
1年以上 → 支払い方法の変更(償還払い)
1年半以上 → 一時差止
2年以上 → 減額 となります。
4 設問の通りなので、そのまま覚えておきましょう
5 ややこしい内容ではありますが、介護保険法第183条の2の内容です。覚えてきましょう。
問題18 要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
2 地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。
3 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
4 要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
5 更新認定の申請は、有効期間満了の日の 60 日前から行うことができる。
解答 2・5
1 申請をするのは市町村です。介護認定審査会は市町村に設置される附属機関で、要介護認定等の審査・判定を行います。
2 基本的に申請は被保険者本人が行いますが、申請の代行ができるところがあります。
1 指定居宅介護支援事業者
2 地域包括支援センター
3 介護保険施設
4 地域密着型介護老人保険施設
5 社会保険労務士
6 民生委員
3 「更新認定の申請に限って」というところが間違いですね。申請代行は、新規、更新、区分変更があります。
4 認定の流れをしっかりと理解しておくことが大切ですね。医師の診断書を取り寄せるのは市町村です。よく引っ掛けで出題されます。申請の時に提出する書類は
第1号被保険者→申請書、介護保険被保険者証
第2号被保険者→申請書、医療保険証 ※第2号被保険者は原則、介護保険証は交付されていません。
5 設問の通り。60日前からです。
問題 19 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。
2 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
3 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
4 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
5 審査及び判定の基準は、市町村が定める。
解答 1・2
1 設問の通り、介護保険法にそのように規定されています。
2 設問の通りです。基本的には、自分が加入している保険者が認定調査を行ますが、住所地特例対象に施設などに入所している場合は、保険者である市町村の担当者が調査に行くのは大変なので、他の市町村に嘱託することができます。
3 新規認定調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができます。
4 特記事項、主治医意見書は2次判定で使用されます。
5 審査及び判定の基準は国が定めており、全国一律となります。
問題52 介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。
2 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、
機能訓練指導員として勤務することができる。
3 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用
いて利用者の状態を把握することは認められていない。
4 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える
取組のために必要な時間を含めることはできない。
5 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要
な訓練を行わなければならない。
解答 2・5
通所介護とは、居宅サービスに含まれています。利用定員は19人以上です。利用定員が19人未満は地域密着型通所介護です。
1 人員基準についてですが、管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員の配置が必要です。
管理者は、特に専門的な資格は必要ありません。常勤・専従で1人以上です。(兼務可)社会福祉主事任用資格が必要なわけではありません。
2 看護職員は、他の業務と兼務できますので、機能訓練指導員としての業務をすることもできます。
3 生活機能向上連携加算についての内容ですね。設問のような内容であれば、生活機能向上連携加算Ⅱを算定することが可能です。
4 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、サービス担当者会議、地域ケア会議などの時間も含まれます。
5 設問の通りです。
問題53 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減
を図るものでなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる
場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。
3 夕食時間は、午後5時以前が望ましい。
4 食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うこ
とが望ましい。
5 いかなる場合も、利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。
解答 1・2・4
1 短期入所生活介護の目的として、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減がありますので正しいです。
2 設問の通りです。そのように覚えておきましょう。
3 かなり変化球な問題と感じますが、午後5時以前だと生活リズムとしては、少し早いように感じますね。
4 食事の提供のも短期入所生活介護の内容に含まれています。
5 基本的には定員を超えての利用はできませんが、虐待や、災害など、やむを得ない理由があるときは定員を超えての利用は認められる場合があります。
問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
2 リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
3 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
4 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
5 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
解答 1・3・5
1 住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。同一住居に複数の被保険者がいる場合があります。例えば、ご夫婦で生活していて、お二人とも介護保険の認定を受けているとします。このような場合は、それぞれ住宅改修費の支給を受けることができます。
2 住宅改修の項目に「段差の解消」がありますが、リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象にはなりません。住宅改修は工事が必要になります。
3 設問の通りです。和式便器から洋式便器への取り替え。便器の位置や向きの変更も対象になります。
4 「浴槽内すのこ」は特定福祉用具になります。購入が対象になるものです。福祉用具購入費の支給対象となます。トイレやお風呂に使用するものは、「購入」と覚えておくといいですね。
5 設問の通りです。住宅改修の内容の内容に、付帯工事があります。
①手すりの取り付け ②段差の解消 ③床または道路面の床材の変更 ④引き戸への取り替え ⑤様式便器への取り替え ⑥付帯工事